����҂̒n��ړ����玦����鐶���\���̕ϗe�Ɓs�V�N��@�t
�\�A�����J�n�����gTHE OREGONIAN�h�́u���җ��𗓁v���e���́\
�Ћˁ@���Îq
1.�@���̏���
�@�����\���i1�j�̕ϗe�ɂ́A�Ⴆ�Έ����z���Ƃ��������Z�n�ړ����܂ޒn��ړ��i2�j�A�g�߂Ȑl�ԊW���ς��p�[�\�i���E�l�b�g���[�N�̕ω��A�a�C��̒��s�ǂ��܂߂��g�̓I�ٕρA�]�E�E���i��ސE�Ƃ������d���ʂł̕ω��i3�j�A�����E�č��Ƃ������Ƒ��W�̈ڂ�ς��A�@�����Ȃǂ������邱�Ƃ��ł���B���̂悤�ɑ��`�I�Ȑ����\���̕ϗe�Ɋւ��Đ������邽�߂ɁAD.���r���\���m1978��1992�n�́u�ߓn���v�Ƃ����T�O�����Ă���B�ߓn���ɂ́A����܂ł̐����\�����I���ɂ��āA�V���������\����z���\�������܂��B���̎����ɍs�Ȃ����I���́A�����\���ɉ��₩�ȕω����邢�͌������ω��������炷���Ƃ��������Ă���B�u����������č�������A�]�E������A�����z��������A�������C�����ĖL���ɂ��Ă����V��������͂��߂��肷��v�m���F104�A�����͕M�ҁn�B
�@�{�e�ł́A�����\���̕ϗe�̂Ȃ��ł��A�Ƃ�킯���r���\���̎w�E����u�����z���v�ɒ��ڂ���B��̓I�ɂ́A����҂́u�����z���v�Ƃ����n��ړ��ɒ��ڂ��A������A����Ҍl�ɂƂ��Ă̐����\���̑傫�ȕϗe�̈�Ƒ�����B���̏�ŁA�u�����z���v�Ƃ����n��ړ����s�Ȃ������ƁA�l�̐l���ɂ������@�Ƃ��Ắu�ߓn���v�����т��čl�@�����݂�B�{�e�̖��S�́A����Љ�̑����F���������߂��Ƃ��āA����Ҍl�̒n��ړ��ɏœ_�āA���U���B�̊ϓ_����u�V�N���v�ɂ�����s�V�N��@�t�Ɓs�V�N�̍Ő����t�̑��݉\����j���ʂɎ����邱�Ƃł���B
2.�@D.���r���\���́u���N��@�v���s�V�N��@�t�ւƕ~�������鎎��
�@2.1�@D.���r���\���ɂ�����u���N��@�v�Ɓu���N�̍Ő����v
�@D.���r���\���́A�t���C�g�A�����O�A�G���N�\���Ƃ������S���w�̐�s�����Ɋw�тu���l�̔��B�̊�{�I�����v�m���F19�n�Ȃ���̂��A�Љ�S���w�I�ϓ_����w��I�ɉ𖾂��悤�Ǝ��݂��B���Ȃ킿�A���l������l�Ԃ̔��B���I�����Ă��܂��̂ł͂Ȃ��A���U�ɂ킽���Ă��ꂪ�p�������Ƃ�������ł���B���ꂱ���A�܂��ɐ��U���B�_�̓`���I�����ł���Ƃ����悤�B�ނ́u�����\���v�Ƃ����L�C�T�O��p���āu���B�idevelopment�j�v�T�O�����̂悤�ɋK�肵���B���B�Ƃ́A�����E�Ƃ̔��B�Ƃ����������̈�ʂɂ��Ă̔��B�ł͂Ȃ��A�u�����\���̔��W�ievolution
of the life structure�j�v�m���F85�n�ł���A�ƁB���������āA���l�̔��B���w��I�Ɍ������邽�߂ɂ͐����\���ɒ��ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂����r���\���̊�{�I�A�C�f�A�ł���B���̐����\�������グ�Ă�����̗v�f�́u�I���ichoices�j�v�m���F89�n�ł��邪�A�I���̖{���͐l�ɂ���ĈقȂ�B�����������������������\���̖{�����𖾂���ɂ́A�l���̗��ꂪ��̓I�ɔc���ł���l�j���L���ł���B�����ŁA���r���\�����40�l�̒j���̌l�j�ׂāA���l���̐����\���̔��W���u������v�i�����\�����z����鎞���j�Ɓu�ߓn���v�i�����\�����ω����鎞���j�̘A���I�����ߒ��ł��邱�Ƃ��������i4�j�B
�@���̂悤�ɁA�l���S�̂ł݂�A�l�͉ߓn���ƈ�������J��Ԃ��o������B�����A���r���\���͊����āu�l�����̉ߓn���v�ł���u���N��@�v�ɒ��ڂ��A���̊�@�����̃��C�t�E�X�e�[�W�Ƃ͎��I�ɈقȂ邱�Ƃ��������B�����A����ɕt�����Ĕނ͐l���ő�̊�@�Ƃ������ׂ��u���N��@�v�����z������ɂ́u���N�̍Ő����v��������Ƃ��đ��݂���Ƃ������Ƃ����킹�ĕ�������ɂ����B���̂悤�ȃp���_�C���ɏ]���āA���r���\���͒��N���܂ł́u���l�̔��B�̊�{�I�����v���𖾂����̂ł���B������������A�̎��т́A�Ώێ҂�j���Ɍ��肵�Ă͂�����̂́A���U�ɂ킽��u���B�Љ�w�v�̊�{�I�g�g�ݍ\�z�����݂��ŁA�傫�ȃq���g��^���Ă����Ǝv�����i5�j�B
�@2.2�@D.���r���\���ɑ���ᔻ�I�����\A.S.���b�V�AJ.A.�N���[�Z��
�@�������A���r���\���̒m���ɑ���ᔻ�����݂���B�Ⴆ�AA.S.���b�V�͎��̂悤�Ȕᔻ�I�����������Ă���B���r���\����̌����ɂ͒��N���́u�l�X�̐����̒��ł͐��m�ɉ����A�Ȃ��ω����Ă���̂��Ƃ������͖������̂܂c����Ă���v�m187�n�A�ƁB���������āA�����̒��N�j���ɕK���u���N��@�v���K��A��������z������ɂ͕K���u���N�̍Ő����v�����݂��A���[�����������\�������艻���邱�Ƃ��ł���Ƃ����u�W���I��@���f���v�͓K�ł͂Ȃ��A�ƃ��b�V�͎w�E����B�Ȃ��Ȃ�A���r���\���́u���N��@�v�T�O�ɂ́u��@�̊T�O���m�����Ă��Ȃ����A�����̓�����Ȃ���Ă��Ȃ��v�m188�n�̂�����B
�@�܂��AJ.A.�N���[�Z���́A���C�t�R�[�X�_�ɂ�����u���B�\�Љ�\�K���v�̊ϓ_����A���r���\����̌������ʂł���u�����\���v�A�u���B�ۑ�v�A���邢�́u�i�K�⎞���v�Ƃ����������̊T�O�ɑ��Ď��̂悤�Ȕᔻ�������Ă���B�l���ɂ͗l�X�Ȑ��ڂ����݂��邪�A���̐��ڂ���@�ɂȂ�Ƃ��ɂ́A����͂قƂ�ǎЉ�I�����ƊW���Ă���B�����A���N��@�ɂ��ċc�_����Ȃ�A�����ɂ́u����̔N��⎞���Ɋ�@�𑣂��T�^�I�ȏo������A��@�����ۂɑ��݂��Ă���Ƃ�����悤�Ȋ�v�m1986��1987�F242�n������͂��ł���B�����A���r���\���̊T�O�ɂ͂��ꂪ�Ȃ��B�܂��A�ނɂ�鐶���\���̉�́i�ߓn���j�ƁA���̌�̐V���Ȑ����\���̍č\�z�i������j�̌J��Ԃ��Ƃ����l���͂��������A�ƃN���[�Z���͔ᔻ�����Ă���B�l�Ԃ͏̕ω��ɉ����ĐV���ɓK�����ĕω����Ă������߁A�u��������A�ނ���Ȃ���v�m���F243�n�Ƃ����咣�ł���B
�@���̗��҂̔ᔻ�́A���r���\���̃L�C�T�O�ł���u�����\���v�̌���ɂ��Ƃ��낪�傫���ƍl������B�����ŁA�M�҂Ȃ�ɂ��������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B�܂����b�V�́A���r���\���̒����ł͊�@���K��錴���◝�R�����m�ɒ���Ă��Ȃ����Ƃɒ��ڂ��A���N��@���u�W���I��@���f���v�Ɖ��߂��Ă���B�������Ȃ���A����͌�����������ł���Ǝv����B�Ȃ��Ȃ�ޏ��́A�����\���̓������\�l�\�F�ł���Ƃ������r���\���̎w�E�����Ă���̂�����B�����������ׂĂ̐l�Ԃ��ꗥ�ɋ��ʂ̐����\�����Ȃ��A���̊�@�����ʂɂނ����Ă���Ƃ������Ǝ��̉��߂ɂ���āA������u�W���I��@���f���v�Ƃ������t�ŕ\�����Ă��܂��Ă��邱�Ƃɂ��^�₪����B
�@���ɁA�N���[�Z���̔ᔻ�́A�l�̐l���Ɋ�@�������炷�悤�ȋ��ʂ̎Љ�I���Љ�I�o�����̎��_�����r���\���ɂ͌����Ă���Ƃ������̂ł���B�����A���r���\���́u���W�v�m108�n���A����l�̐l���ɒ������e����^����o�����ƒ�`���āA�N���[�Z���̂����K���̊ϓ_�����łȂ��A���B�̊ϓ_����������I�Ɍ������Ă����K�v������Ƃ��w�E���Ă���B�Ⴆ�A�푈�A�ЊQ�A�s���A�����A�a�C�A��������̂̑r���Ȃǂ����W�Ƃ��čl�����邪�A�l�Ԃ͂����������o�����ɒP�ɓK�����Ă��������ł͂Ȃ��B���B�_�ɂ�����ǂ̎����\�\���l�O���A���N���A���邢�͘V�N���\�\�ɓ��W���ނ����A���ꂪ�l�̐����\���̔��W�ɂǂ�ȉe�����y�ڂ��̂��ɂ��Ă܂ŁA���r���\���͕��L���l�����Ă���B
�@�ȏ�̍l�@�ɂ��A��l�̔ᔻ�����r���\���́u���N��@�v��u���N�̍Ő����v��V�N���ɂ܂Ŋg�傷�鎎�݂�j�ނ��̂ł͂Ȃ��̂ŁA�{�e�ł͊�{�I�ɂ̓��r���\���̃p���_�C�����̗p�������B
�@2.3�@�s�V�N��@�t�Ɓs�V�N�̍Ő����t�̑��݉\��
�@�����ŁA���r���\�������炩�ɂ����u���N��@�v�Ɓu���N�̍Ő����v��~�������邩�����ŁA�s�V�N��@�t�Ɓs�V�N�̍Ő����t�̑��݉\���������邱�Ƃ����݂�B����ɂ��̎��݂�j�������łȂ��A���������˒��ɓ���Ēj����r�Ƃ����������ōs�Ȃ������B
�@�\1�ɂ݂�悤�ɁA���r���\���́A���C�t�E�X�e�[�W��傫���u�����N���v�i0���`17���j�A�u���l�O���v�i18���`39���j�A�u���N���v�i40���`59���j�A�u�V�N���v�i60���`79���j�A�u�ӔN���v�i80���`�j�ɕ��ނ��āA�e���C�t�E�X�e�[�W�̔��B���ɂ����Ĕ��B�i�K�ɉ������ו����s�Ȃ��A���ꂼ��ɖ��̂������B���r���\���͒��N�j��40�l�ւ̐����j�������ɂ��A���̍ו��𒆔N���܂ōs�Ȃ������A�{�e�ł͂����~�������āA�V�N���ƔӔN���ɂ܂œK�p���Ă݂����B�������܂Ƃ߂�ƕ\1�ɂȂ�B
�\1�@���r���\���ɂ�锭�B�i�K
|
���C�t�E�X�e�[�W |
�e���B���ɂ����锭�B�i�K |
�w�W�Ƃ��Ă̔N�� |
�����̐��i |
|
�����N�� |
�\ |
�`17�� |
�\ |
|
|
���l�ւ̉ߓn�� |
18���`22�� |
�ߓn�� |
|
���l�O�� |
���ƂȂ̐��E�֓��鎞�� |
23���`28�� |
����� |
|
|
30�̉ߓn�� |
29���`33�� |
�ߓn�� |
|
|
��Ƃ��\���鎞�� |
34���`39�� |
����� |
|
|
�l�����̉ߓn�� |
40���`45�� |
�ߓn�� |
|
���N�� |
���N�ɓ��鎞�� |
46���`49�� |
����� |
|
|
50�̉ߓn�� |
50���`55�� |
�ߓn�� |
|
|
���N�̍Ő��� |
56���`59�� |
����� |
|
|
�V�N�ւ̉ߓn�� |
60���`65�� |
�ߓn�� |
|
�V�N�� |
�V�N�ɓ��鎞�� |
66���`69�� |
����� |
|
|
70�̉ߓn�� |
70���`75�� |
�ߓn�� |
|
|
�V�N�̍Ő��� |
76���`79�� |
����� |
|
�ӔN�� |
�ӔN�ւ̉ߓn�� |
80���`85�� |
�ߓn�� |
|
|
�l���̔ӔN�� |
86���` |
�\ |
�i�o�T�j���N���܂ł̓��r���\���m1978��1992�F111�n�ɂ��쐬�A�V�N���ȍ~�͕ЋˁE���тɂ�镪�ށB�Ȃ��A�\���̘V�N���ɂ�����S�V�b�N�̂́A�{�e�Ŏ��������s�V�N��@�t�Ɓs�V�N�̍Ő����t�������B
�@���̂悤�ɖ{�e�Ŏ����������Ƃ́A�u�l�����̉ߓn���v�Ƃ��Ắu���N��@�v�i40���`45���j�Ɓu���N�̍Ő����v�i56���`59���j�����łȂ��A�u�l���㔼�̉ߓn���v�Ƃ������ׂ��s�V�N��@�t�i70���`75���j�Ɓs�V�N�̍Ő����t�i76���`79���j�̑��݉\���ł���B
3.�@�����̊T�v
�@3.1�@���җ��𗓁iOBITUARY INDEX�j�ɂ���
�@�{�����̑f�ނƂȂ����f�[�^�́A�A�����J�̃I���S���B�E�n�����gTHE
OREGONIAN�h�́u���җ��𗓁i�I�r�`���A���E�C���f�b�N�X�j�v�ł���B�P�Ȃ�u���җ����v���g�M�d�Ȑ����j�f�[�^�h�Ƃ݂Ȃ����킯�ł���B
�@�gTHE OREGONIAN�h���́A�K������1�ŁA�Ƃ��ɂ�2�łɂ킽���āu���җ��𗓁v���f�ڂ��Ă���B����͑��V��⎀�҂̈⑰�ɂ���Ē�o����A�t���[�E�T�[�r�X�Ŋ��蓖�Ă�ꂽ�X�y�[�X�Ɉ������Ă����i6�j�B�Ⴆ�A1997�N10��1���̎��җ��𗓂Ɍf�ڂ���Ă����l�̂Ȃ�����K���Ȑl��j����l�Â����Ă݂����B������90�ŖS���Ȃ������V�[��.E.D.B����A�j����88�܂Ő������X�e�t�@��.E.T���ł���B
|
A funeral will be at 2 p.m. Wednesday,
Oct., 1997, in Riverview Abbey Funeral Home for Lucille E. DeCicco Benedetti,
who died Sept. 27 at age 90. Mrs. Benedetti was born Aug. 7,1907, in Proctor, Minn. Her
maiden name was Nubson. She lived in Portland since 1916 and was a homemaker.
She married Michael F. DeCicco in 1925; he died in 1963. She married Raymond
Benedetti in 1965. Survivors include her husband;
daughters, Gloria M.Aarseth of Hillsboro and Delores G. Dedrickson of
Beaverton; sister, Jean Dimmick of Gresham; 13 grandchildren; 14
grate-grandchildren; and two grate-grate-grandchildren. Private interment will be in Riverview
Abbey Mausoleum. The family suggests remembrances to Emanuel Children�fs
Hospital. |
|
A memorial service will be at 10:30
a.m. Thursday, Oct., 1997, in Trinity Episcopal Cathedral for Stephen Eberly
Thompson, who died Sept. 28 at age 88. Mr. Thompson was born Nov. 10, 1908,
in Vancouver, Wash. He married Helen Malarkey in 1934. He served in the U.S.
Navy during World War�Uand was a staff aide and flag lieutenant for Adm.
George D. Murray. He received a Bronze Star. He was an executive vice
president of M&M Plywood Co. of Portland and retired in 1956. He
previously was president of Douglas Fir Plywood Corp. in Tacoma. Mr. Thompson served on the boards of
the Medical Research Foundation of Oregon, the Pacific-International
Livestock Exposition, Portland General Electric Co, Lewis & Clark College
and the University of Portland. Survivors include his wife; sons,
Stephen of Sisters, George of Portland and Neskowin; and daughter, Victoria
Brockman of Portland and Gearhart. A daughter, Kitty Ellis, died in 1996. Interment will be in Riverview Abbey. |
�@3.2�@�����Ώێ�
�@1997�N10��1������10��30���܂łɁA�����ɏЉ���悤�Ȃ������Łu���җ��𗓁v�Ɍf�ڂ��ꂽ797�l�̂����A60�Έȏ�̕��ŃO���C�^�[�E�|�[�g�����h�n��iMetro
Area�j�ŖS���Ȃ�����712�l�i�j��351�l�A����361�l�j��Ώێ҂Ƃ����B���̌��͑S����797�l�̎��җ������Љ�ꂽ�B���̊��Ԃ̂Ȃ��ŁA��ԑ�������55�l�A���Ȃ�����14�l�A���ς��Ĉ��25�`26�l�ł������B797�l�̎��җ����҂̂Ȃ��ŁA60�Έȏ�̐l��712�l�ł��邩��A���̔䗦��89.3���ɂȂ�B
�@3.3�@�g�l�j�̊�{���h�̐ݒ�ƃf�[�^����
�@���r���\���͐����\���̓����ׂ邽�߂Ɍl�j�̕��������ڍׂɎ��{�����B�{�����ł͂��̕��@�Ɋ�{�I�Ɉˋ����āA�l�j�������̑���ɁA��l�ЂƂ�́u���җ����v�L���̓��e���͂��s�Ȃ��A��������g�l�j�̊�{���h�Ȃ���̂������o���đf�f�[�^�Ƃ����B�g�l�j�̊�{���h�Ƃ́A���̂Ƃ���ł���B���Ȃ킿�A�u�@�o���N���A�o���n���B�R���o�����C�|�[�g�����h���Z�N���D�|�[�g�����h���Z���R���E���Z���̃��C�t�E�X�e�[�W���F���Z���Ƒ��`�ԁ��G���S���̔z��҂̗L�����H���S���̈⑰�̗L�����I���S�N��v�B
�@�܂����ɁA�����g�l�j�̊�{���h��10���ڂ�Ɨ��ϐ��Ƃ��Đݒ肵�A�j����r��O���ɃN���X�W�v���s�Ȃ����m�ЋˁE����1999�F166-212�n�B������Ė{�e�ł́A����ɓ��v�I������{���A�g�l�j�̊�{���h�̃f�[�^����{�I�����Ƃ��Ĕc�����A�j���ԂŗL�Ӎ������邩�ǂ����m�F�����i7�j�B
�@����܂��đ��ɁA���N���܂ł̒n��ړ��ɒ��ڂ���B���Ȃ킿�A�l���u�����z���v�Ƃ����n��ړ������{�����N����AD.J.���r���\�������I�ȕ��@�ŋ敪�������B�i�K�́u�w�W�Ƃ��Ă̔N��敪�v�Ɉˋ����Đ�������B��̓I�ɂ́A�ނ��K�肵�����N���܂ł̔N��敪�ɂ����āA�u�l���̉ߓn���ɂ͒n��ړ��������Ȃ���A������ɂ͂��ꂪ���Ȃ��v���Ƃ�������B����A�u���N��@�v�Ɓu���N�̍Ő����v�����݂��鎖�����������A���r���\���̃p���_�C���ւ̈ˋ��\���͂���B
�@��O�ɁA�V�N���ƔӔN���̒n��ړ��ɒ��ڂ���B���Ȃ킿�A���N�������łȂ��A�V�N���ƔӔN���ɂ����Ă��܂��A�u�l���̉ߓn���ɂ͒n��ړ��������Ȃ���A������ɂ͂��ꂪ���Ȃ��v�X�������邱�Ƃ��f�[�^���番�͂��邱�Ƃ����݂�B�ŏI�I�ɂ́A�s�V�N��@�t�Ɓs�V�N�̍Ő����t�����݂��邱�Ƃ��A�f�[�^���玦�����邱�ƂɂȂ�B
4.�@�f�[�^�̕��͌���
�@4.1�@��{�I�����ɂ���
�@�\2����\5�́g�l�j�̊�{���h��O���ɂ����Ēj���ʂɃN���X�W�v�������̂ł���B�T���v���̊�{�I�����ɂ��āA�j����r���ӎ����g�l�j�̊�{���h�ɉ����Ă݂Ă������B
�@�܂��A�o���N�Ɋւ��āA1910�N��܂łɐ��܂ꂽ�Ώێ҂́A�j��52.4���A����65.7���ł���A�����̕����������Ƃ��킩��B�t��1920�N��ȍ~�ɐ��܂ꂽ�Ώێ҂́A�j���̕��������B����͒j���ԂŗL�Ӎ����o�Ă���A�����̒����𗠂Â��Ă���i��2��9.13�Ad.f.��3�Ap��0.028��0.05�j�B���ɏo���n�ɂ��ẮA�ǂ̒n��̏o�g�҂ł����Ă��A�j���ԂŗL�ӂȍ����قƂ�ǂ݂��Ȃ������i��2��1.65�Ad.f.��5�Ap��0.895�j�B��������́A�T���v���ɕ肪���Ȃ��Ɣ��f�ł���B����ɁA�\2�ɂ݂�悤�ɁA�R���o���Ɋւ��ẮA�j���ԂŗL�Ӎ������m�ɏo�Ă���B�u�R���o������v�̏ꍇ�A�j����57.8���ł���̂ɑ�������1.9���ŁA���|�I�ɒj���̕����R���o���̑������Ƃ�������B
�\2�@�R���o��
|
�R���o�� |
���� |
�Ȃ� |
N |
|
�j�� |
57.8% |
42.2% |
351 |
|
���� |
1.9% |
98.1% |
361 |
��2��267.4�@d.f.��1�@p��0.001
�@���ɁA�Ώێ҂̃|�[�g�����h���Z���̗l�q���݂Ă������B�܂��A���Z�N�ɂ��ẮA�j���Ԃ̗L�Ӎ��͊m�F�ł��Ȃ����i��2��6.01�Ad.f.��4�Ap��0.199�j�A�j���Ƃ��u1930�`40�N��v�ɒn��ړ����Ă���l�q���f����B����ɁA���̗��R�Ɋւ��ĕ��͂���ƁA�j���́u�d���̂��߁v��61.8���A�����́u�n�o�Ƒ��̂��߁v�i�v�̓]�Ɉꏏ�ɕt���Ă��邽�߂Ƒz���ł���j��28.0���ƂȂ��Ă���A�j���ňقȂ������R�ɂ��n��ړ������Ă��邱�Ƃ��ǂݎ���B�܂��A�u�P�A����邽�߁v�̒n��ړ��ɂ����ẮA�j��8.1���A����18.0���ł���A�j�����������̕����A���̗��R�ɂ��n��ړ��Ɣ�r���Ă��������Ԃ�����B����Łu���^�C�A�̂��߁v�̒n��ړ��́A�j��8.5���A����5.4���ƂȂ��Ă���A�u�P�A����邽�߁v�Ƃ͈���ď������j���̕��������i��2��63.64�Ad.f.��5�Ap��0.001�j�B
�@����ɁA���Z���̑Ώێ҂̃��C�t�E�X�e�[�W��c�����Ă������B�j���ԂɗL�Ӎ��͔F�߂��Ȃ����i��2��1.95�Ad.f.��3�Ap��0.583�j�A�u���l�O���v�i18���`39���j�̒n��ړ������|�I�ɑ����X�����F�߂���B�܂��A���Z���̉Ƒ��`�Ԃɂ��Ă��A�\3�ɂ����Ēj���̊ԂŗL�ӂȍ��͂Ȃ��i��2��0.25�Ad.f.��2�Ap��0.882�j�B�������A�j���Ƃ��ߔ����́u�n�o�Ƒ��Ɓv�Ƃ��ɃO���C�^�|�E�|�[�g�����h�n��ɗ��Ă���B
�\3�@���Z���̃��C�t�E�X�e�[�W
|
���C�t�E�X�e�[�W |
�����N�� |
���l�O�� |
���N�� |
�V�N�� |
N |
|
�j�� |
33.9% |
38.0% |
14.9% |
13.3% |
316 |
|
���� |
35.9% |
31.7% |
13.1% |
19.3% |
306 |
��2��1.95�@d.f.��3�@p��0.583�@�L�Ӎ�������Ƃ͂����Ȃ�
�@�Ώێ҂̎��S���̗l�q�����킹�ďЉ�Ă������B�\4����́A�Ώێ҂��S���Ȃ����Ƃ��̔z��҂̗L�����킩��B��������g�v���ȂɁu�旧���āv�S���Ȃ�A�Ȃ��v�Ɂu�旧����āv�S���Ȃ�h�Ƃ����p����������ɂȂ�B����ɁA�z��҂Ɍ��肳��Ȃ��⑰��ʂ̑��݂Ɋւ��Ă��A�j����94.9���A������89.9�����u����v�ŁA�j���Ƃ��⑰�����݂���B�����A�j���ɔ�ׂď����̂ق����⑰�����݂��Ȃ��P�[�X�������i��2��6.55�Ad.f.��1�Ap��0.011��0.05�j�B�Ō�ɁA���ώ����ɂ��ẮA�j��77.52�A����81.14�A���v79.36�ł���A�j������3.62�Ɛڋ߂��Ă����B
�\4�@���S���̔z��҂̗L��
|
�z��� |
�旧�� |
�旧����� |
N |
|
�j�� |
68.7% |
31.3% |
339 |
|
���� |
26.4% |
73.6% |
341 |
��2��122.20�@d.f.��1�@p��0.001
�@�������āg�l�j�̊�{���h�ɉ����Ȃ���A�Ώێ҂̊�{�I�������A�j����r���ӎ����A���̑S�̑�������ɂ��Ă����B
�@�ȉ��ł́A�u���N���v�ȍ~�i40���`�j�Ɋւ��Đ��U���B�̎��_����A���������j������O���ɒu���A�l�́u�����z���v�Ƃ����n��ړ��ɏœ_�ĂāA�|�[�g�����h���Z���ɂ�����Ώێ҂̃��C�t�E�X�e�[�W�̕��͂����Ă����B
�@4.2�@���U�ɂ킽��u�ߓn���v�Ɓu������v�̘A���I�����FD.���r���\���̎��ؕ���
�@���r���\���m1978��1992�n�͓O��I�Ɍl�j�����A�Ώێ҂́u�����\���v�͂��邱�Ƃɂ��A�e���B���ɂ����锭�B�i�K�Ƃ��̎����̐��i�i�ߓn���ƈ�����j�𖾂炩�ɂ����m�\1���ēx�Q�Ɓn�B�ȉ��̌����ł́A�l�����Z�n�ړ����܂ޒn��ړ����s�Ȃ��������A�l���ɂ����ČJ��Ԃ������u�ߓn���v��u������v�Ƃǂ�Ȋ֘A�������邩��͍������i8�j�B
�@�}1�́A�Ώێ҂��|�[�g�����h�ɗ��Z�����N����A���r���\���ɂ�锭�B�i�K�ɃJ�e�S���[�����āA���̐���j���ʂɎ��������̂ł���B���̐}���݂Ĉ�ڂł킩�邱�Ƃ́A�ߓn���ɒn��ړ��������Ȃ���A������ɂ͒n��ړ������Ȃ��_�ł���B�������A���̌X���́u�l�����̉ߓn���v�i40���`45���j�ȍ~�ɓ��Ă͂܂邱�Ƃɒ��ӂ��Ă��������m�t�ɐ��l�O���ł͂���Ƃ͔��̌X�����݂���n�B
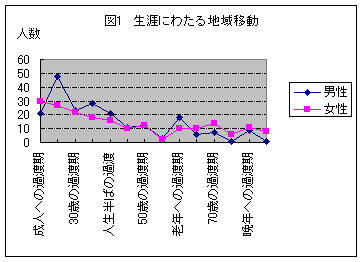
�@4.3�@�s�V�N��@�t�Ɓs�V�N�̍Ő����t�̑���
�@���r���\�������I�Ɏ������u�ߓn���v�����p���āA�{�����ł́u�����z���v�Ƃ����n��ړ��ɏœ_�Ăĕ��͂����Ƃ���A�m���ɁA�ߓn���ɒn��ړ��������X�����m�F���ꂽ�B�����D.���r���\���ɂ��u���N��@�v�Ɓu���N�̍Ő����v�̍Ċm�F�ɂȂ�ł��낤�B����ɁA�V�N���ɕ~��������ƁA���N�������łȂ��V�N���ɂ����Ă��A�ߓn���ƈ�������J��Ԃ��Ă��邱�Ƃ����������B���A�V�N�������ɒ��ڂ���ƁA���N���Ɠ��l�A�ߓn���ɒn��ړ��������Ȃ���A������ɒn��ړ������Ȃ��X�����݂�ꂽ�B���Ȃ킿�A�u�V�N�ւ̉ߓn���v�i���ߓn���j�A�u70�̉ߓn���v�i���ߓn���j�A�u�ӔN�ւ̉ߓn���v�i��O�ߓn���j�ɒn��ړ��������Ȃ���A�u�V�N�ɓ��鎞���v�A�u�V�N�̍Ő����v�ɂ͒n��ړ������Ȃ��Ȃ��Ă���m�}2���Q�Ɓn�B���̎����́A�܂��Ɂs�V�N��@�t�Ɓs�V�N�̍Ő����t�����݂��邱�Ƃ��������Ă���ƍl�����邪�A����̎��،����ɂ��V���������Ƃ�����̂ł͂Ȃ��낤���B
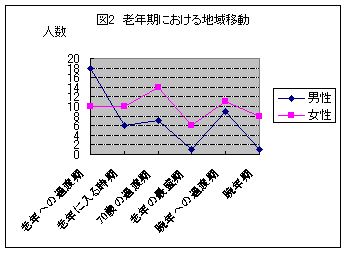
�@�������A�\5����A�V�N���ɂ�����ߓn���ƈ�����̂ނ������Ɋւ��āA�j���ԂɗL�Ӎ������݂��邱�Ƃ��w�E�ł���B�j���̉ߓn���ɂ�����n��ړ���81.0���ŁA������ł�19.0���ł���B����A�����͉ߓn����59.3���A�������40.7�����n��ړ������Ă���B�����̃f�[�^���͂ɂ��A�V�N���ɂ����ẮA�����̕����j���ɔ�ׂāA������ɂ����Ă������n��ړ����s�Ȃ��X�����m�F���邱�Ƃ��ł����i9�j�B
�\5�@�V�N���ɂ�����n��ړ�
|
�V�N�� |
�ߓn�� |
����� |
N |
|
�j�� |
81.0% |
19.0% |
42 |
|
���� |
59.3% |
40.7% |
59 |
��2��5.30�@d.f.��1�@p��0.021��0.05
�@����ɁA�V�N���Ƀ|�[�g�����h�ɗ��Z���闝�R�ʂ̕��͂��s�Ȃ����m�}3�A4���Q�Ɓn�B��ɁA�P�A����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ă|�[�g�����h�Ɉڂ�Z�ށu�P�A�E���|�ҁv�ƁA�d����ސE������ňڂ�Z�ށu���^�C�A�E���|�ҁv�̓�̃^�C�v�ł����i10�j�B����ŁA�u�P�A�E���|�ҁv�́A�O�q�������ߓn���Ƒ�O�ߓn���ɒn��ړ����Ă���P�[�X���j���Ƃ������X��������B�����Łu���^�C�A�E���|�ҁv�̐��́A���ߓn���ɒn��ړ����Ă���ꍇ���j���Ƃ������Ƃ�����B
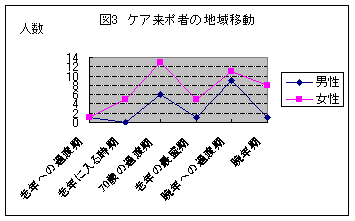
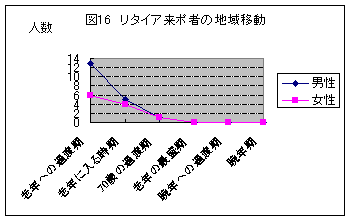
5.�@�l�@�ƌ��_
�@�ȏ�̒j����r��O���ɒu�������͌��ʂ���A���̎l�̓_�����炩�ɂȂ����B���ɁA��{�I�����̕��͌��ʂ��A�V�N���ȍ~�̒n��ړ����A���l�O���⒆�N�����܂߂��S�̂̒n��ړ�����݂�Ə����h�ł��邱�Ƃ����������B�j���Ԃ̗L�Ӎ��͊m�F�ł��Ȃ��������A�Ƃ�킯�j���ɂ�邱�̎����̒n��ړ��̏��Ȃ��������ł���X���͓ǂݎ�ꂽ�B�܂��A�n��ړ�����l�I�ȗ��R�Ɋւ��ẮA�����́u�P�A����邽�߁v�������A�j���́u���^�C�A�̂��߁v��������������������ɂȂ����B
�@���ɁA���U���B�̊ϓ_����͎��̂��Ƃ����������B���Ȃ킿�A�u���N���v�ɂ�����u�l�����̉ߓn���v�i40������45���܂Łj�ȍ~����A�ߓn���ƈ������4�`6�N�P�ʂŌ��݂ɌJ��Ԃ��A���u�����z���v�Ƃ����n��ړ����s�Ȃ��P�[�X���A�ߓn���ɂ͑���������ɂ͏��Ȃ��Ƃ����X�����m�F���ꂽ�B�����������X�����Ċm�F���闝�R�́A�����\���̕ϗe����_�@���u�����z���v�Ɍ��肵�Ă͂�����̂́A���r���\����ɂ�锭�B�i�K�̃p���_�C���Ɉˋ��ł��邱�Ƃ��咣���邽�߂ł���B
�@����܂��đ�O�ɁA�u�V�N���v�ɏœ_�ĂĂ��A���̂悤�ȌX�������l�ɂ݂��邱�Ƃ��������ꂽ�B���̏�A���N���ɂ�����u���N��@�v�Ɓu���N�̍Ő����v�̑��݂����łȂ��A�V�N���ɂ�����s�V�N��@�t�Ɓs�V�N�̍Ő����t�̑��݉\�����A�f�[�^���畂������ɂ��ꂽ�B�Ⴆ�A�j���Ƃ��s�V�N�̍Ő����t�i76������79���܂Łj���ł��n��ړ������Ȃ��Ȃ��Ă���B���̂悤�Ȏ������琄�@����邱�Ƃ́A���̎������߂����l�������A���ʂ̔��B�ۑ���N���A���Ď������v�����ׂ������b��Ȃǂ������A�ł����肵���u�����\���v��z���Ă��邽�߂ƍl������B
�@�u�V�N���v�ɒn��ړ������l�̉ߓn���͎�ɎO�i���ߓn���`��O�ߓn���j����Ƃ����ɕ��ނ������A�u���^�C�A�E���|�ҁv�͑��ߓn���i60���`65���́u�V�N�ւ̉ߓn���v�j�ɍł������n��ړ����A�u�P�A�E���|�ҁv�͑��ߓn���i70���`75���́u70�̉ߓn���v���s�V�N��@�t�j�Ƒ�O�ߓn���i80���`85�́u�ӔN�ւ̉ߓn���v�j�̗������ɑ����n��ړ�������X��������B�O�҂͒j���ɑ����A��҂͏����ɑ����݂�ꂽ�B���̎������������Ƃ́A�����u�V�N���v�ɂ�����ߓn���Ƃ͂����Ă��A���̓������傫���قȂ��Ă���\�������邱�ƁA���Ȃ킿���z����ׂ����B�ۑ�̓����̍��قł���B�u���^�C�A�E���|�ҁv�̔��B�ۑ�́A�d�������߂邱�ƂɂƂ��Ȃ��u�����k���ߒ��v�m���q1993�F41�n�̔F���Ƃ��̉����ł���A�u�P�A�E���|�ҁv�̔��B�ۑ�́A�g�̘̂V�����ۂɂƂ��Ȃ��u�����I�g�̂̉t�I�E�s�t�I�ٕρv�ɑ���{���l���ł���m�Ћ�1998�n�ƍl������B
�@�Ō�ɖ��炩�ɂȂ������Ƃ́A�V�N���ɂ����āA�����̒n��ړ��͉ߓn���Ɍ��炸������ł������A�j���̒n��ړ��͉ߓn���ɑ���������ɂ͏��Ȃ��Ƃ������Ԃł���B���̓_�ɒj���ԂŗL�ӂȍ������m�ɕ\�ꂽ�B��������A�V�N���ɂ����āA�����͐����\�������肵���ł̒n��ړ��𑽂��o�����A�j���͐����\�����s����ȏł̒n��ړ��𑽂��o������A�Ƃ������߂�������B����܂���ƁA�����̕����j�������A���z����ׂ����B�ۑ�Ƃ̗��݂�����A��r�I�]�T���������u�����z���v���s�Ȃ��X��������Ƃ����悤�B
6.�@�������ʂƍ���̉ۑ�
�@���U���B�_�ɂ�����e���B���́u�ߓn���v���A�u�����z���v�Ƃ����n��ړ����s�Ȃ������ɏd�ˍ����Č������Ă����B�u�����z���v�Ƃ����v�f�͉ߓn���ɂ�����u�����\���v�̕ϗe�̈�_�@�ł���ɂ�������炸�A�ߓn���ɂ͈����z���̃P�[�X������������ɂ͂��ꂪ���Ȃ��Ƃ����X�����c�����ꂽ���Ƃ́A�{�����ɂ������̐��ʂł���ƍl���Ă悢�B�Ȃ��Ȃ�AD.���r���\�������I�Ɏ������u���N��@�v�Ɓu���N�̍Ő����v���A�����ł͎��I�f�[�^�̑�ʕ��͂ɂ�藠�Â��A����ɂ����V�N���ɂ܂ŕ~�������ās�V�N��@�t�Ɓs�V�N�̍Ő����t�̑��݉\����������������ł���B
�@�������A�u���җ��𗓁v�̃f�[�^���̂̏��Ɍ��E�����邽�߁A�V�N���ɂ�������ߓn���A���ߓn���A��O�ߓn���̓����̈Ⴂ���A�{�����ł͋�̓I�Ɏ������Ƃ��ł��Ȃ������B����͑�ʒ����̌��E�ł���B�܂��A�ߓn�����ނ�����͉̂����u�����z���v�Ƃ����n��ړ��Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��A���ɂ��l�X�Ȃ������ʼnߓn�����ނ����邱�Ƃ��\�z�����B���̈Ӗ�������A����Ƃ����I�������s�Ȃ��K�v������B�Ⴆ�A�j���̏ꍇ�A���N���܂ʼn�Бg�D�̂Ȃ��ŁA��������������Ƃ������o�ϊw�I�s�v���_�N�e�B�r�e�B�t�ɉ��l�u���������o���Ă������A���^�C�A��ɔ@���ɂ��Ă��̉��l�u�����A�Љ�w�I�s�v���_�N�e�B�r�e�B�t�i11�j�ɓ]�������Ă������B���̂����A����Ҍ����̗��ꂩ��A����Łs�V�N��@�t��l���㔼�́u�ߓn���v�ƈʒu�Â��A�����Łs�V�N�̍Ő����t��V�N���ɂ�����u������v�ƈʒu�Â���B�s�V�N�̍Ő����t�́u�����\���v�̓������g�v���_�N�e�B�u�E�G�C�W���O�h�ɂ�����Љ�w�I�s�v���_�N�e�B�r�e�B�t�Ƃ��Ĕc�����A�C���e���V�B�u�Ȓ����ɂ���Ă��̖{���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ�����̉ۑ�Ƃ������B
�m�r���n
�i1�j���{�ɂ�����u�����\���v�̊T�O������߂đ��l�ł��邪�A��ʂɂ͎��̎O�̗̈�A�@�Љ���I�̈�A�A�����̌n�_�I�̈�A�B�s�s�Љ�w�I�̈�A�ɕ��ނ��邱�Ƃ��ł���B�܂��A�@�Љ���I�̈�ɂ�����u�����\���v�T�O�̐����͍ł��Â��B���t���e�Ƃ������ׂ��U�R���m1943�n�́A1��24���Ԃ̐������\�����Ȃ��Ƃ��A1����J���A�x�{�A�]�Ɏ��Ԃɕ��ނ����B���ɁA�A�����̌n�_�I�̈�ɂ����ẮA���c�`��m1971�n�̐����\���̏z���Ƃ����A�C�f�A������B�������̐��Y�ł���Ƃ��A�u�����̐��Y�������̏��������i�̐��Y��������i�̏���ĂсA�����̐��Y���c�c�v�Ƃ����z�����u�����\���v�ƋK�肵���B�Ō�ɁA�B�s�s�Љ�w�I�̈�ɂ������؍L�m1976�n�ł́A�l��Ƒ�����̂Ɉʒu�Â��A�u������̂������̌n����юЉ�\���ɐڂ���A���ΓI�Ɏ����I�ȃp�^�[���ł���v�Ƃ��Ă���B�����A�{�e�ł�D.���r���\���m1978��1992�n�̋K�肷��u�����\���v�T�O�Ɉˋ�����B����ɂ��Ɛ����\���Ƃ́u���鎞���ɂ����邻�̐l�̐����̊�{�p�^�[���Ȃ����v�v�m85�n�ł���B���̊T�O��p���邳���ɂ́u���ȂƊO�E�̗������A�����Ă��̑��݊W���l���ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�m85�n�B����ɁA�����\�������W���Ă����l�q�ׂ�ɂ́u�l�j�̌`�v�m87�n���Ƃ�̂��悢�B�u�����\���̒��S�ɒu�����v�f�͈�Ȃ�����v�m90�n�ł���A����ȊO�͎��ӂɒu�����Ƃ����B
�i2�j�n��ړ��Ƃ́A�u�o�g�n�i15�̍��Z��ł����ꏊ�j�ƌ��݂̋��Z�n�̊Ԃ̈ړ��v�m�ˌ��E���сA260�n�̂��Ƃł���B�n��ړ����c�_���邳���̎��Ƃ��āA�ނ�́u�ړ��̕����v�Ɓu�ړ������v�̓��p���Ă���B�O�҂ɂ��Ắu�S������s�s�ւƂ�������v���T�^�I�ł���A��҂Ɋւ��ẮA�ߋ����ړ��ƒ������ړ����L���ł���B�{�e�ł́A�f�[�^�̓�����A�|�[�g�����h�s���܂߂āA�n�����gThe
Oregonian�h�𒆐S�I�ɍw�ǂ���n����u�|�[�g�����h��s�s���v���邢�́u�O���C�^�[�E�|�[�g�����h�n��v�ł���ƋK�肵���B���̏�ŁA�|�[�g�����h��s�s���ւ̗��Z�҂��A�ߋ����ړ��Ⓑ�����ړ��̔@���ɂ�炸�u���|�ҁv�Ƃ��A�����n��ړ��Ƃ݂Ȃ����B�܂��A�|�[�g�����h��s�s�������ړ�����҂͒�Z�҂Ƃ��Ĕc�����A����͒n��ړ��Ƃ݂Ȃ��Ȃ������B
�i3�j����͊K�w�ړ��Ɋ܂܂��B�����������K�w�ړ��́A�n��ړ��ƂƂ��ɎЉ�ړ��̈ꕔ�Ƃ��Ă��ʒu�Â��邱�Ƃ��ł���m�O�Y�A63�n�B�Љ�ړ��Ƃ́u�l�̎Љ�I�n�ʂ̕ω��v�ł���ƒ�`�����B���������āA���̈ړ����㏸�����~���Ƃ������Ƃ����ɂȂ�B�����{�e�ɂ����ẮA�u���җ����v�Ƃ����f�[�^�̐����A���̊K�w�ړ����㏸�ړ��ł��邩�A���邢�͉��~�ړ��ł��邩�Ɋւ��镪�͂͂��Ȃ������B
�i4�j�u������v�́u�Љ�ɒn�����ł߂�v�m���r���\���E��F250�n�Ƃ����������e�i���X�i�ێ��j�ł���A�u�ߓn���v�́u����ɗ�ށv�m���n�Ƃ������p�t�H�[�}���X�i�Ɛсj�ł���Ƃ�����ɑg�D�_�ɂ����郊�[�_�[�V�b�v�_�Əd�ˍ��킹�邱�Ƃ��ł���ł��낤�B
�i5�j���r���\���́A�Ȃ̃W���f�B�Ƌ��ɁA�����̐��U���B�ɂ��Ă��Ȗ��Ȏ��ؒ����m1996�n���s�Ȃ��Ă���B����ɂ��ƁA�ނ�͒����Ώێ҂��A��Ǝ�w�ƃL�����A�E�E�[�}���̓�^�C�v�ɕ����Đݒ肵�A�����̔��B�i�K����{�I�ɒj���̂���Ɠ����ł���ƌ��_�Â��Ă���B
�i6�j�V���Ђւ̖₢���킹�ɂ��ƁA�O���C�^�|�E�|�[�g�����h�n��ŖS���Ȃ����l�̂ق�99�����u���җ��𗓁v�ɓ͂��o�Ă���ƍl���Ă悢�B
�i7�j�{�e�̕��͂́A��{�I�ɂ͎��ᕪ�͂ł���B�����A����̗ʂ��������ʁA�X�̏��͏��Ȃ��Ƃ������E�����B�����₤���߂ɓ��v�I������قǂ������B
�i8�j�������A�����z��������l�����ׂĐl���̉ߓn���I�ɂ���킯�ł͂Ȃ��B������ł����Ă������z�����s�Ȃ����Ƃ͓��R�ł���B�����A�{�e�ł́A�����\���̕ϗe�Ƃ����u�l���̉ߓn���v���Ђ��N�����悤�ȗl�X�Ȍ_�@�̂Ȃ��ł��A�Ƃ�킯�u�����z���v�Ƃ����n��ړ��ɏœ_���i�邱�Ƃ��s�Ȃ����B
�i9�j���r���\����̌����ɂ��ƁA���B�i�K�͒j���Ƃ������敪�ł���m1996�n�B�܂�A�}1�̔��B�i�K�́A�j���ɂ����ł͂Ȃ������ɂ��܂��K�p�ł���B���������āA�����ł͒j�����̕��͂��\�ɂȂ�B
�i10�j�V�N���ȍ~�ɂ�����n��ړ��̗��R���A����2�̃^�C�v�i�u�P�A�E���|�ҁv�Ɓu���^�C�A�E���|�ҁv�j�ɍi���ĕ��͂������̂́A����痼�^�C�v���V�N���̒n��ړ��ɂ����鑼�̂ǂ�ȗ��R�����ۗ����Ă������߂ł���B
�i11�j�u�v���_�N�e�B�u�E�G�C�W���O�v�̊T�O��R.�o�g���[�ɂ���Ē��ꂽ�B����́A����҂������J�����Ȃ����ߔY�I���݂ł���Ƃ������悤�ȁA�_�b�Ƃ��Ă̍���ґ��ւً̈c�\�����Ăł���B�t�ɁA�ނ���A�Ⴂ�Ƃ�����L���ɔ|���Ă����������g���āA�L���Љ��L���ɂł��鑶�݂ł���Ƃ����咣�ł���B���̍l�����������u�v���_�N�e�B�u�E�G�C�W���O�v�ł���B�M�҂̉ۑ�̈�́A�����������A������ɂ�����v���_�N�e�B�r�e�B�ɏœ_�āA�Ȗ��Ȏ��ؒ����ɂ��A����ɓ�����^���邱�Ƃł���B
�m�����n
�m1�nA.S.Rossi,�gAging and
parenthood in the middle years�h in Paul B. Baltes, and Orvile G. Brim,Jr.(eds.),Life-Span Development and Behaveior,1980,Vol.3,pp.137-205,Academic
Press.�i���m�E���،b�q�E�����b�q�ҏW�^�Ė�1993�w���U���B�̐S���w�x��3���w�Ƒ��E�Љ�x�V�j�Ёj.
�m2�n D. J. Levinson,1978, �gTHE
SEASONS OF A MAN�fS LIFE�h, New York : Knopf.�i�씎��1990, �w���C�t�T�C�N���̐S���w�i��j�E�i���j�x�u�k�Њw�p���Ɂj.
�m3�nD. J. Levinson,1996, �gTHE SEASONS OF A
WOMAN�fS LIFE�h,Ballantine Books.
�m4�n���c�`�璘1971�w�����\���̗��_�x�L��t.
�m5�n John A. Clausen ,1986, �gThe
Life Course: A Sociological Perspective�h, Prentice-Hall �i�����c�K�E�����Ζ�1987�w���C�t�R�[�X�̎Љ�w�x����c��w�o�ŕ��j.
�m6�n�U�R����1943�w���������̍\���x���剮���[.
�m7�n���q�E��1993�w�s�s����Љ�ƒn�敟���x�~�l�����@���[.
�m8�n�Ћˎ��Îq���u���������鏗���́q���ȕ\���r�ɂ݂�v���_�N�e�B�r�e�B�\�������ɂ�����u�����v�Ɓq�e���ȑ��ҁr�̊ϓ_����\�v�i1998�N�x�A�C�m�_���j.
�m9�n�Ћˎ��Îq�E���ѕ� ����1999�u�A�����J����҂̒n��ړ��Ɛ����ϗe�\�w�W�E�I���S�[�j�A���x���́u�I�r�`���A���[�E�C���f�b�N�X�v���́\�v�w���U�w�K�����N��xNo.6�A131-237,�k�卂������@�\�J�������Z���^�[���U�w�K�v�挤����.
�m10�n�O�Y�T�q�u�R�~���j�e�B�ɂ�����y���Ɨ����v63-89�A��؍L��1978�w�R�~���j�e�B�E�����[���ƎЉ�ړ��̌����x�A�J�f�~�A�o�ʼn�.
�m11�n�O�Y�T�q�E�X�����u�E���X�؉q��1986�w���[�f�B���O�X���{�̎Љ�w5�@�����\���x������w�o�ʼn�.
�m12�nR.M.���[�i�[�EN.A.�u�b�V��=���X�i�[�K����1981,
�gIndividuals as puroducers of their development�h Academic Press,����c��q��1990�w���U���B�w�@�l���̃v���f���[�T�[�Ƃ��Ă̌l�x���w�p�o�Ŏ�.
�m13�n��؍L��1976�w�Љ�w�T�_�x�L��t.
�m14�n�ˌ��C��E���я~��u�Љ�K�w�ƈړ��ɂ�����n��̖����\�o�g�n�Ƌ��Z�n�\�v232-271�A�x�i�����1979�w���{�̊K�w�\���x������w�o�ʼn�.